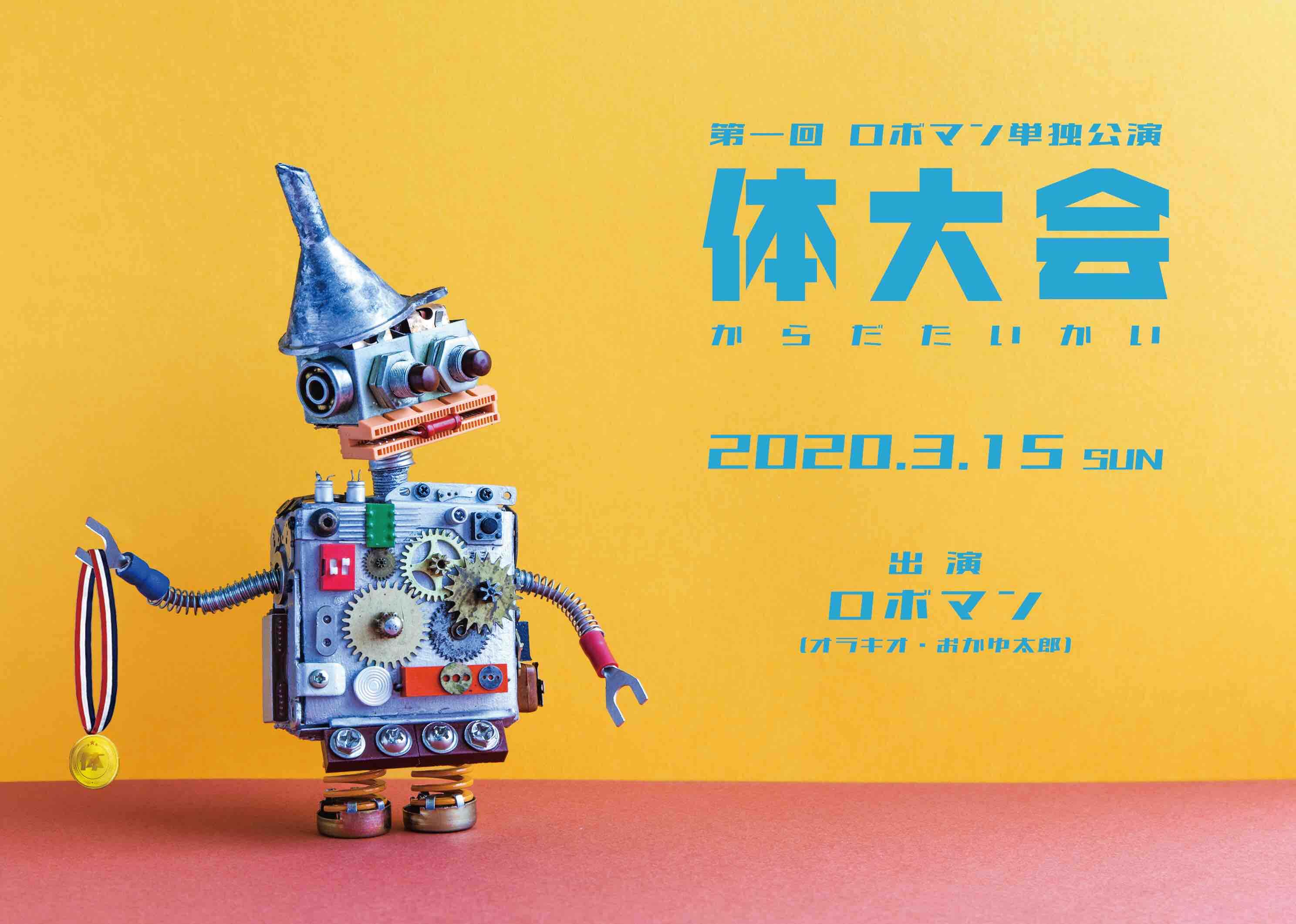ドイツ版『ゴット・タレント』で優勝を目指す「ゆんぼだんぷ」が掲げる”お笑い3.0”とは?

現代日本における「お笑い」の歴史について考える時、避けて通ることができないのが「世代」による変遷である。クレージーキャッツに始まり、ザ・ドリフターズ、とんねるず、ダウンタウン、ナインティナイン。数多くのお笑い芸人たちが、それぞれの時代で日本のお笑い界を築き上げてきた。
2018年のM-1グランプリで優勝を飾った「霜降り明星」のせいやが、自分や同世代のお笑い芸人を「お笑い第七世代」を呼んだことが話題になった。お笑い第七世代は、インターネットやSNSとの親和性が高く、テレビという枠に囚われない若い世代として、これからの活動が期待されている。「お笑い第七世代」という見方を、お笑い界における縦軸とするならば、「ゆんぼだんぷ」がやろうとしているお笑いは横軸であり、世代のくくりに縛られない、いわば「お笑い3.0」と呼べるものだろう。
2015年『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』に出演して優勝を収めた「ゆんぼだんぷ」は、ブレイクのきっかけとなった音ネタを武器に海外進出を果たし、2019年の12月には『ダス・スーパータレント』の決勝戦に進出することが決まった。いわゆる普通のお笑い芸人とは違うキャリアパスを歩んでいるふたりは、なぜ日本を離れて海外にに行くことを決めたのか。そして、これからどこへ行こうとしているのか。決勝戦の放送を前に、「ゆんぼだんぷ」のふたちにお話を伺った。

―――『ダス・スーパータレント(ドイツ版の『アメリカズ・ゴット・タレント』)』の決勝進出、おめでとうございます。まずは、おふたりの率直な気持ちを聞かせていただけますでしょうか?
藤原大輔(以下、藤原):色々な国の『ゴット・タレント』に出させてもらっているんですけど、決勝は初めてのことなので、かなりワクワクしてますね。
カシューナッツ:ドイツ(のゴット・タレント)は、他の国の『ゴッド・タレント』と比べて「良い意味で変な人」を使うっていうのが、僕が見た限りの特徴なんです。もうすでに、1回戦に出た人たちの動画が続々とインスタとかFacebookとか公式YouTubeにアップされているんですけど、それがもう、すごい変な人ばっかりで……。
―――変というのは?
カシューナッツ:僕が見たのは、おばあちゃんぐらいの年齢の女性の方なんですけど、Jカップぐらいの巨乳でドレスを着て出てきて、舞台上の台にバットを置いて「巨乳でそのバットを叩き折る」っていう芸を披露したんです。「僕ら、こんな人と戦って勝てるんかな」って、正直思いましたね。次はスイカを取り出して、おっぱいでスイカを叩き割る。「なんじゃこれ」って感じなんですけど、会場も大爆笑なんです。他にも、舞台上に本物の馬を連れて来た人がいて、「何をするのかな」と思ってたら、音楽に合わせて「ヒヒーン」「ブルッ」って言うんですよ、馬が。それだけなんですよ。シュールで、めちゃくちゃ面白い。「俺たち、馬と戦ってるのか」って戦慄しましたね。M-1(ぐらんぷり)で馬と戦うことってないじゃないですか? 変な戦いというか、変な場所にいるなと常々思いますね。
藤原:決勝は12組なので、何としてでも優勝したいと思っています。
―――色々な意味で、かなり激しい戦いになりそうですね。
―――同じ『ゴット・タレント』でも、国ごとに違いはあるのでしょうか? たとえば「ウケるネタが違う」や「お客さんの雰囲気が違う」のような。
カシューナッツ:結構違いますね。『ゴット・タレント』で言うと、今までに5ヶ国以上の国でやったんですけど。「ウケるネタが違う」というよりは、「ここでは裸がNG」みたいな、マナーや宗教が理由の制限が多かったですね。
藤原:文化的な背景なんかもそうで、たとえば「音の聞こえ方」も国によって違いが出てくるんです。日本だとニワトリ(の鳴き声)は「コケコッコー」じゃないですか? でもアメリカでは「クックドゥードゥルドゥー」なんです。そういう違いがあるから、音ネタをやるにしても下調べが必要で、ネタをやる前に現地の人に聞いてからタイトルを考えるようにしています。
―――国ごとにネタもアレンジしないといけない?
藤原:こっちは「びっくりしたのカエルの音」だと思って鳴らしてるんですけど、向こうの人からは「それはアヒルの声だ」みたいに言われたりする。全然違うんですよ。
カシューナッツ:最終的には「向こうの人が見るもの」になるので、ネタはそちらに合わせないといけないんです。
藤原:僕らにとっては、「面白い・面白くない」以前に「ちゃんと伝わるか・伝えられるか」が心配なんです。
―――「笑いは世界の共通言語」と言われることもありますが、やはり文化や言葉の壁は大きいのですね。
カシューナッツ:僕たちが初めて出た『ゴット・タレント』がマレーシアだったんですけど、「裸はいいけどおへそを出すのはNG」っていう謎のルールがあったんです。
―――ここより下はNG、ということでしょうか?
カシューナッツ:いや、おへそがダメなんです。それで、過去の出場者を見たら、たしかに(おへそに)番組ステッカーみたいなのを貼ってるんですよ。それで、僕らのネタはお腹を合わせて音を鳴らすので、へそがかなり大事になってくるんです。シールを貼ってしまうと音が出なくなるんですよ……(笑)「へそは無理だ」と言われてしまって、「そうなるとネタができなくなってしまう」とかなり交渉したら、最終的に「収録の時に、君たちの出番を遅くする。だいぶ遅い22時以降になると思う」と伝えられたんです。なんでも、収録現場にそういうコンプライアンスをチェックするスタッフがいるらしいんですが、22時を回ったらそのスタッフが帰るから、ということだったんです。
―――帰ってしまったらやってもいいと?
藤原:収録だから、どちらにせよ後で編集する時に怒られそうな気もしたんですけど、「撮ってしまったら仕方ない」みたいな感じらしいんですよね。厳しいんだか緩いんだか、いまいち分からない。そういう曖昧なところも海外らしさがあって面白かったですね。
―――『ダス・スーパータレント』で気を付けなければいけないことはありましたか?
カシューナッツ:これは番組に限らず、ドイツでは絶対にやってはいけないことなんですけど、日本の漫才師って、舞台に出てくる時に片手をあげて出てくるじゃないですか? あれはもう、絶対にダメです。(※ナチス式敬礼を連想させるため)
藤原:「命を狙われるレベルのことなので、絶対にやめてください」と直前に言われて、めちゃくちゃ気になってしまいましたね。僕らも入場の時に手を振って入って行くんですけど、「止めたらヤバい」って思ってしまって、絶対に止められないんです。
カシューナッツ:本番前は、ネタの練習よりも手を振る練習をしてました。
―――ネタを披露している時、「お客さんの反応」や「笑いのツボ」などが日本と海外で違うと感じることはありますか?
藤原:かなり違いますね。向こうは拍手をする文化なので、いいパフォーマンスを見ればちゃんと拍手してくれるんです。ネタが終わったあとはもちろん、ネタ中でもスタンディングオベーションが起きたりするんです。
カシューナッツ:舞台に出る人に対して、一定のリスペクトみたいなのがあるんです。誰が出る場合でも、必ず拍手をして迎えるし、拍手をして帰す。きちんとリアクションがあるんですよ。逆に、面白くなかったらちゃんとブーイングが起こります。ネタ中であっても関係ないし、僕らが静かにしていて欲しい時でもブーイングが起きてしまったりする。お客さんの感情がストレートに伝わってくるんです。
藤原:そのあたりは、日本のお笑いのファンとはちょっと違う感じがしますね。日本だと、まずは「何が出るんだ?」って感じで、グッと堪えて静かに見るし、笑う時も周りに遠慮してしまう方が多いと思います。
カシューナッツ:たとえば、向こうはネタ中にBGMで音楽を使うとしたら、それに手拍子をするのが当たり前なんです。こっちが煽ったりしなくても何も言わずにそうなるし、指笛まで鳴らす。「ノリがいいな〜」と思いますね。
藤原:だから僕らも、なるべくノリがいい曲を使ったりして、お客さんに盛り上がってもらうような作戦を取るようにしています。
―――純粋な面白さだけではなく、会場を巻き込めるかどうかが大事になってくる?
カシューナッツ:そうですね。上手い人はそういうのがすごく上手いですね。お客さんと一緒に何かをやったりとか。極端な話、本当にネタが面白くなくても、名曲を使うだけで場を沸かせられるんです。マイケル・ジャクソンとかヤバいですよ。
藤原:神です、本当に。ネタも何もしてないのに盛り上がってるんですよ……(笑) まあ、その盛り上がりは自分たちの力ではないので、勘違いしないように気を付けつつも、上手く活用していきたいなと思っていますね。
―――これは「どっちが良い悪い」という質問ではないのですが、海外でネタを披露するのと日本でネタを披露するの、どちらの方に気持ち良さがありますか? おふたりのお話を聞いていると、海外の方がよさそうかなと思ってしまうので。
藤原:「気持ち良さ」に的を絞ると、断然海外になってしまいますね。
カシューナッツ:そうですね。でも、海外の場合だと、今パッと思った言葉とかを表現できないので、細かいことができないという歯痒さはあります。例えば日本だと、お客さんの中に変にうるさい人がいたら、それいじって笑いを取ったりもできる。他にも、音ネタをやって、終わった後の感想の一言とかで笑わせたりするんですけど、言語の壁があると、そういう笑わせ方は選択肢から消えてくるんです。
藤原:僕たちのネタに「イルカの求愛」っていうネタがあって、曲を流しながらネタをやるんですけど、アメリカでやった時に「反応がよすぎて曲が聴こえなかった」っていうことがありましたね。
カシューナッツ:あれはびっくりしましたね。めちゃくちゃにウケて、拍手もすごくて、でもそのおかげで曲が全然聴こえなくてネタがしづらかったんですよ。
―――お客さんのノリのよさが裏目に出てしまう時もある?
藤原:よく歌手の人がコンサートとかで耳にイヤホンを付けてるじゃないですか? その時は、「あれ欲しいな」って思いましたね……(笑)

―――今でこそ音ネタで知られている「ゆんぼだんぷ」のおふたりですが、結成された当初は普通の漫才師として活動されていたと伺いました。そこから現在のスタイルにシフトしていった経緯を教えていただけますでしょうか?
藤原:元々僕らは大阪松竹で出会いまして、9年間ぐらい大阪で活動していたんですけど、その頃は漫才とコントばかりしていました。
カシューナッツ:大阪は東京よりもさらに「賞レース」と呼ばれるものが数が多いので、「とにかく賞レースを獲れ!」みたいな意識が強かったんです。
藤原:「漫才師になりたい」「しゃべくり1本で行きたい」みたいなプライドもありましたね。
カシューナッツ:深く考えたりはせず、そういう周りの流れに乗っていたという感じですね。もちろん、今考えたら大事なことなんですけど。漫才は他のお笑いにも通ずるので、ネタの基本的なことを勉強できますから。……ただ、僕たちは漫才で何の結果も出せていなかったんです。本当に、あらゆる賞レースの予選で落ち続けていたんです。オーディションにも呼ばれず、大阪では仕事がない状況が長く続いて、ふたりで「これからどうしよう」と悩んでいたんです。

カシューナッツ:その時に「せめて、何かひとつでも、テレビに出るための強みを作ろう」という話になったんです。さっきも言ったんですけど、大阪は賞レースの社会なので、賞レースがオーディションみたいな感じで、予選落ちの芸人にはチャンスさえないんです。だから、違う場所―――東京に出て色々なオーディション受けてみよう、と考えたんです。それでも全部ダメだったら、それは本当に(お笑い芸人として)ダメということじゃないですか? それなら諦めがつく。でも、そのチャレンジさえせずに、チャンスのない今の状況で終わってしまうのは嫌だなと。そこからふたりで話し合って、「1回東京に行こう」「そのためには、テレビ出るための何かが必要だ」「オーディションに引っかかるためのネタが必要だ」という結論になったんです。
藤原:そんな話し合いをしている時に、たまたま「音ネタ」が生まれたんです。
―――偶然にネタが生まれた?
カシューナッツ:当時の大阪のマネージャーと3人でサウナに行っていた時、サウナの中でそのマネージャーさんが「来月の仕事が決まったぞ」って言ってくれて、本当に久しぶりの仕事だったので、僕たちでふたりで「やったー!」みたいな感じでハイタッチをしようとしたんですよ。そうしたら、ふたりともちょっと太っていたので、手よりも先にお腹の肉がぶつかったんです。その時に、あの「チョンッ」っていう音が鳴ったんです。(※ 「まるで鏡のような水面に雨のしずくが一滴落ちる音」というネタ。フジテレビ系列で放送されていた『とんねるずのみなさんのおかげでした』内のコーナーである『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』で披露され、お茶の間を席巻した)
藤原:「何これ!?」みたいになって、「今のをネタにできるんじゃないか」みたいなことをそこで話して、タイトルを付けて、という流れであのネタが生まれたんですよ。本当に偶然、奇跡です。サウナだから汗でお腹も濡れていて、コンディションとしては最高にいい状態だったんです。
カシューナッツ:そもそもふたりでハイタッチすること自体、そうそうないというか。
藤原:裸なんて、もっとないですよね。
カシューナッツ:その頃は何も仕事がなくて、嬉しい事も何ひとつなかったので、ハイタッチとは無縁だったんです。サウナにいた横の知らないおっちゃんも、その音を聴いてちょっと笑っていたので、「これで何かできるんじゃないか」と閃いて。
―――本当に奇跡から生まれたということですよね。
藤原:もし服を着ていたら、あの音は鳴っていなかったです。
カシューナッツ:今考えたら無謀なんですけど、僕たち、そのネタ1個だけ持って上京したんです。大阪での(事務所)ライブは3軍、2軍、1軍みたいに分かれていて、僕たちは3軍のライブに出ていたんですね。そこで初めて(そのネタを)披露しまして、僕としてはかなり自信があったんですけど、お客さんは全然ウケていなくて票数も伸びなかったんです。20組中10位みたいな結果。「やっぱりダメなのかな」と思ったんですけど、楽屋に戻ったら、尊敬する先輩とか周りの芸人が「さっきのあれ、めちゃくちゃ面白い」って言ってくれたんです。今思えば、あの反応が全てでしたね。同じ芸人がみんな「面白い」って言ってくれたので、それに勇気付けられて「これ1つで東京行くか」って決めたんです。僕が28歳で藤原が30歳の時でした。それで、上京して最初に出た番組が『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』だったんです。
―――そこで、見事に優勝しました。
藤原:そこからは、ずっと音作りでしたね。僕らはネタ作りではなく「曲作り」って呼んでます(笑)僕も、もっといい音を鳴らすために1年で40キロ太りました。
カシューナッツ:当時の藤原は、ほぼほぼ普通の体型だったんですよ。7、80キロでちょっとお腹が出てるぐらい。僕は今と変わらなかったので、大阪にいた時は僕のデブをいじるネタとかをやっていたんですけど、今はもうできないですね。
藤原:僕がちょっと声が高いので、「声が高い方と血糖値が高い方でやってます」みたいな掴みをやってたんですけど、今はふたりとも血糖値が高くて……(笑)
カシューナッツ:そんな面白くもない掴みを9年間もやっていたんですよ。先輩の芸人さんの中には「その音ネタと一緒に漫才もやっていけ」って言ってくれる方もいたんですけど、かなり悩みながらも、僕らは元々漫才もコントもあんまりよくなかったからこういうスタイルになったので、漫才もコントも捨てることにしたんです。振り切った方が面白いかな、って。だから、今は本当に1個も作ってないんですよ。
―――世間的には「お笑い芸人と言えば漫才かコント」というイメージが極めて強いです。おふたりがその決断を下すのには、かなりの勇気が必要だったのではないですか?
藤原:コントや漫才のネタは相方が作っていたんですよ。それで、ある時から突然、ネタを書いてこなくなったんです。その時に、「ああ、音ネタ1本で行くんだな」って感じて、だから、はっきりと言ったとかではなく、自然とそうなっていたんです。
カシューナッツ:上京して、『細かすぎて〜』で音ネタがウケて、そこから色々な仕事やライブに出られるようになったんです。その時はまだ血気盛んというか、大阪時代の名残りもあって「賞レース全部獲るぞ!」みたいな感じで、一応漫才もやっていたんです。でも、まあウケなくて……(笑) 逆に、音ネタ以前に裸で登場するだけで会場が「ワッ」となるみたいなのが続いて、「もうこれ無理やな」って思ったんです。東京に来てから色々な芸人と知り合いになったんですけど、僕が面白いと思う芸人さんや先輩方が口を揃えて、「漫才は面白くない」って言ってたんです。悲しいけど、「それが真実なんだろうな」と。
藤原:僕たちが面白いと思う人が「面白くない」って言ったということは「面白くないんだな」ということなんです。その言葉がなかったら、まだ漫才をやっていたと思います。それがいいのか悪いのかはともかく……。
カシューナッツ:海外に進出しようと思ったのも、(バナナマンの)設楽さんが「このネタ海外でウケるよ」って言ってくださったのがきっかけですし、『ゴット・タレント』に出たのもタンバリンマスターのゴンゾーさんがアドバイスをくださったからなんです。そういう意味では、「ゆんぼだんぷ」は周りのアドバイスに助けられていると思います。
藤原:周囲の人に恵まれていると感じます。周りに人がいなかったら、こうはなっていない。
カシューナッツ:なってないですね、絶対。
藤原:今にして思えば、大阪時代の9年間、全くウケてない時に「よく辞めなかったな」と思いますね。
―――おふたりも、当時はやはり「賞レースを獲りたい」という気持ちだったのでしょうか?
カシューナッツ:めちゃくちゃありましたね。
藤原:あるのに1回戦落ちだから、辛い。めちゃめくゃ辛いですよ。
カシューナッツ:漫才を捨てて別のジャンルで勝負しようってなった時、それはそれで応援してくれる人が結構増えたんですよ。お笑い芸人って言うと、「誰しもがM-1グランプリで優勝したがっている」と思われるかも知れないんですけど、「全員が1つのゴールを目指しているわけじゃない」だとか「全員が全員、賞レースのためにお笑いをやっているわけじゃない」って思っている人も少なからずいるんです。コンビだと少ないですけど、ピン芸人の方って割とそういうスタンスの方が多いんですよ。

カシューナッツ:(所属している)事務所は違うんですけど、GO!皆川さんっていう芸人さんがいまして、「ウンチョコチョコチョコピー!」のネタ1つでもう10年以上、それで飯を食ってるんです。そういう生き様を見ていたら「自分を貫くって、かっこいいな」って思うんです。松竹(芸能)の先輩方もそうですね。代走みつくにさんやかみじょうたけしさん、松原タニシさん、森脇健児さんや安田団長。どなたも、「賞レースで結果を出す」というよりも「自分のやりたいことを貫いて仕事にしている」方たちです。クロちゃんもそのひとりかも知れませんね。今や、大スターじゃないですか。松竹(芸能)にはそういう先輩方が多いのもあって、「ブレずにやろう」と腹を括れたのかも知れないですね。
藤原:漫才やコントでちょっとでもウケちゃってたら、こうして海外に行ってないと思うんですよ。振り切ってないから。あえてこの音ネタで振り切ったから、その延長線上に海外への挑戦があったと思うんです。でも、今でも賞レース―――『キング・オブ・コント』とか『M-1(グランプリ)』を見るたびに心には来ますけどね。「かっこいいな」みたい羨望は、正直あります。決勝見てると、グサッと刺さりますね。
―――『M-1グランプリ』は演出も派手ですからね。しかし、おふたりの出られている『ゴット・タレント』も相当かっこいい番組だと思います。おふたりのことを「すごい活躍をしている」と羨んでいる芸人さんも多いのではないのでしょうか?
藤原:嬉しい言葉です。……ありがとうございます。その言葉は、本当に嬉しいですね。
―――実際、周りの芸人さんの反応はいかがですか?
カシューナッツ:応援してくださる方がほとんどですね。
藤原:確かに「すごいな〜!」みたいに言ってくださる方ばかりですね。
カシューナッツ:あとは「ギャラ、いくらだった?」みたい質問が多いかな……(笑) なんなら、海外だと出ないことの方が多いですからね。あとは、「俺も(海外に)行きたいんだけど、どうすればいい?」という相談も頂きますね。「あ、この人も狙ってるんや」みたいな。
藤原:ピコ太郎さんの影響がデカいと思います。あの人が「全ての芸人の考え方を変えた」というか、「現代には、こんな出方があるんだ」と知らしめたんです。飛び級じゃないですけど、もう飛んで飛んで、1番すごい飛び抜け方でしたから。
カシューナッツ:2016年ぐらいからですかね。あの人の影響で、みんな海外やYouTubeに行き始めた。「思っていたほど遠くはないんだ」ということに気付き始めたんです。
―――おふたりが所属されている松竹芸能は、今年の8月にYoutuberやTikTokerなどの「配信タレント」の養成を目指すコースをタレントスクール内に開設しています。カシューナッツさんのお話にもあったように、ひとつのゴール、たとえば「賞レースで優勝すること」だけを目指しているのではない感じがありますよね。
カシューナッツ:そうですね。芸人の側も、あまり縛られてないんです。「絶対に(事務所)ライブに出ろ」とも言われないんです。他の事務所だったら、絶対に出なければいけないみたいな風潮はあると思うので、その辺は自由かもしれないですね。自分のやり方で何か仕事を取ってくる、みたいな人が多い印象です。僕らもネタライブに出続けていたら、漫才やコントを無理くり続けていただろうし、そうなれば今みたいにはなっていなかったと思います。「ひとつのゴール」を目指すのをやめて、「別のルートを探そう」と思ったから、海外に行くことができたんです。
―――ここからは、おふたりの今後についてお話を伺っていきたいと思います。
―――ひとつめは、かなりざっくりとした質問になってしまうのですが、来年日本でオリンピックが開催され、それに伴って外国人観光客が急増することが予想されます。当然、滞在中はテレビを観ることがあるはずですし、「日本のエンターテインメントを楽しみたい」と考える外国人の方は多いと思います。しかし、言語の壁がそれを阻むかも知れません。そういった状況の中で、日本のテレビ業界、あるいはお笑い界は、外国人向けに変わっていくと思われますか? おふたりは、どうすれば外国人も楽しめるようなコンテンツが作れると思いますか?
藤原:確かに、日本のテレビって全部日本語ですもんね。海外の人って、(日本でテレビを)観るんですかね?
―――藤原さんは、海外に行った際にテレビをご覧になりましたか?
藤原:その国のお笑い芸人や、「どんなチャンネルがあってどんな番組をやってるんだろう」というのは気になるので、やっぱり点けるんですけど、観ても言葉が分からないから挫折しちゃいますね。言語の壁はデカいですよね。
カシューナッツ:日本の『SASUKE』って、海外では『Ninja Warrior(ニンジャ・ウォリアー)』っていう名前で放送されているんですよ。『ガキの使い』の「サイレント図書館」なんかも、海外でも評価がすごく高い。世界中で公式・非公式問わず、日本の番組が真似られることがあるようなので、必ずしも「ウケない」という訳ではないんです。言語の壁があるのは仕方ないので、そのぶん「言葉に頼らない笑い」なら、面白ければ絶対にウケる。日本の芸人さんは、どうしても「どう喋るか」に重きを置く人がほとんどだと思うので、そこを主軸にしていたら海外の人に届かせるのは難しいと思います。
藤原:あと、単純にネタをやる番組自体が減っているじゃないですか? それも、お笑い文化を発信するうえではかなりマイナスになっていると思います。さっきも話で出ましたけど、向こうは「ステージへのリスペクト」があるので、そういう系の番組も多いんですよ。賞レースだけじゃなくて、普段からお笑いをやる場が増えればいいのにと思いますね。
カシューナッツ:「外国向け」という目線で言うなら、もっと見た目のインパクトを使っていくべきでしょうね。見た目自体が面白くて、言葉に頼らない笑いをしている人は海外でもそのままウケます。『ゴット・タレント』に出るようになってから、海外進出をしている芸人で集まる機会が多くなったんですけど、吉本のウエスPさんとか、チェリー吉武さんとか、なんとなくみんな『パンチの強い見た目』をしてるんですよね。たとえば、ウーマンラッシュアワーの村本さんとかみたいに英語を完璧に覚えて喋るっていうのも1つの手だと思うんですけど、そうじゃないのなら、自分にできる部分で工夫をしないといけない。……みんな一度、M-1に出場するのを止めたらいいかも知れないですね。そうしたら、「何か違うことをしないと」って考えられるようになるんじゃないかな。
―――M-1グランプリの影響力が大きいぶん、日本のお笑いが「右向け右」になってしまっている?
カシューナッツ:どうしてもそうなりますよね。やっぱり、後輩を見ていても「M-1で勝つぞ!」みたいな子が多いんです。もちろん、それでいいんです。僕らにもそういう時期はありましたし。いいんですけど、それ以外のことにも視野を広げる必要はあると思います。単純に仕事の間口も広がるから。
―――M-1グランプリは1億2000万人の日本人に向けたものですが、海外に向けて何かを行えば、十数億人を相手にできます。
カシューナッツ:正直そうですね。そのぶんチャンスも増えますし、反響の大きさも違う。来年のオリンピックもそうだし、2025年の大阪の万博も控えている。実は今、新宿角座という松竹芸能の劇場で、毎週水曜日に白Aさんが主催している「新宿コメディクラブ」に出演しているのですが、10月なんかは、かなり外国人のお客さんが増えていましたね。ラグビーのワールドカップを観るために来ていた方たちだったんですけど、真っ先に観光客で潤うホテルや飲食店じゃない僕たちですら、如実に観光客効果を感じたんです。ライブ中に「どこからいらしたんですか?」みたいなことを多少を聞くんですけど、イングランドとか南アフリカとか、(ラグビーで)勝ち残ってる国の人が多かった。ワールドカップでこれなんだから、オリンピックになったらものすごいことになるんだろうなって実感しましたね。
藤原:そう考えると、本当に小さなことでもいいから今のうちに何かしら始めておいたら、来年には何かに繋がるんじゃないかなって思いますね。みんながあまりやっていないので、僕らは先にやっておこうと思って頑張っていますけども……(笑)
―――『ダス・スーパータレント』で優勝すれば、オリンピックを待たずに世界中から引っ張りだこになるのでは?
藤原:そうなったら嬉しいですよね。ちなみに去年だと、フランス版の『ゴット・タレント』でウエスPさんが決勝に行っていて、今年からフランスでCMに出てるんですよ。今年、僕らもフランスに行かせてもらったんですけど、フランスの家電量販店―――日本でいうヤマダ電機みたいなところに行ったら、ウエスPさんのパネルが置いてあるんです。ふたりで「ワーッ!」って声出ましたね。そういうレベルなんですよ。だから、やっぱり夢があるなって思いますね。
カシューナッツ:ドイツでは決勝が生放送なんですよ。決勝は12組で、優勝すれば賞金1000万円くらい。それにプラスして、ドイツでのお仕事も入ってくる。『ゴット・タレント』って、スーザン・ボイルさんとかが有名ですけど、要は「一般の人が夢を掴んでスターになる」っていうストーリーを作りたいので、どんな出場者も一般人として扱うんです。だから、僕たちプロの芸人のことも、あくまでも一般人として出したいんです。ネタとかも「これにしてくれ」とか結構指定があって、僕らのやりたい事と向こうの要望が違っていたりするので、メールや電話で何度もやり取りするんです。肝心のネタの方も、ドイツの人にウケるように微調整を続けている段階です。
―――この記事が公開される数日後には決勝が開催されるので、日本からおふたりの優勝を祈っております。
―――それでは、最後の質問になります。オリンピックや万博は「近い未来」の話ですが、もっと先の10年、20年後に「ゆんぼだんぷ」のおふたりがやっていきたいこと、今後の展望について、おひとりずつ教えていただけますでしょうか?
藤原:確かに、これはお互いに気持ちが違うかも知れないですね。
カシューナッツ:そうですね。10年とか、そこまで先の話はさすがにしていないので。

藤原:僕個人としては、歳も36で、まあまあ歳がいっているので、10年後にはこの体型を維持するのが大変になっていると思うんですよ。だから僕、この世界でやっていくには自分が短命だろうな、って思っているんです。それを見越して「僕が倒れた時の代わりのデブ」と言いますか、新メンバーを入れて、また「ゆんぼだんぷ」として始動していけたらな、みたいに考えています。
カシューナッツ:2代目!?
藤原:2代目とか、弟子の育成に携われたらいいなと。たとえば、「自分も『ゆんぼだんぷ』になりたい!」っていう人がいれば、そういう人を集めて会社を作って、世界各地に行ってもらうっていうのもアリだと思ってます。もっと長い年月が経って、「ゆんぼだんぷ」の芸が「世界の芸」として認められていたら嬉しいですね。それで、色々な国に「ゆんぼだんぷ」を派遣していく。アメリカにはアメリカ版の「ゆんぼだんぷ」がいて、マレーシアにはマレーシア版の「ゆんぼだんぷ」がいる。そうなったら、めちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。
―――「ゆんぼだんぷ」という存在がひとつの芸としてパッケージ化される日が来る?
藤原:もちろん、自分が続けられるのが1番いいんですけど、10年後にこの体型を維持できるかは分からないので、そういうのも視野にはあります。「ゆんぼだんぷの音ネタ伝統芸」みたいに継承されていってもいいと思うんですよ。そんな芸人さんっていないじゃないですか?
―――体型の維持はキツいですか?
カシューナッツ:絶対にキツいよ。だって、40キロ増やしたでしょう?
藤原:かなり食べないといけないから、今の時点で生活がしんどいですね……(笑) 体に悪いことして太ったので、多分限界は近いと思うんですよ。
カシューナッツ:僕なんかは昔から太ってるから何もないんですけど、藤原は急激に太ったので反動が来てるんです。靴下が履けなくて、履こうとしたら転けるみたいな。
―――増量という過酷な努力の甲斐あって、あの音は成立しているんですね。
―――それにしても、かなり面白いアイディアだと思います。こういう風に考える芸人さんは少数なのではないでしょうか? 多くの方はプレイヤー思考というか、やはり「自分がステージに立っていたい」という気持ちが強いはずです。
藤原:安心できると思うんですよ。代わりがいるからいつ倒れてもいいんだ、って。太っていて、この衣装さえ着ていたら、海外の人は多分気付かないと思うんです。真面目な話、いつどんなトラブルがあるか分からないから、「違う人でも同じことができる」っていうのは、かなり安心じゃないですか。
―――お笑い芸人のフランチャイズ展開、実際に実現したら面白いですね。
藤原:まずは知名度がないとダメなので、もっと売れないといけませんけどね。世界規模で売れたら、集団、デブの集団を作りたいです。100人ぐらいのデブが集まったデブの会社を。
カシューナッツ:チームA、チームBみたいにね。
藤原:僕らは「元祖ゆんぼだんぷ」っていうことで、弟子を取っていって、まずは体作りから指導したいですね(笑)音ネタのマニュアルも作って、新しい「ゆんぼだんぷ」を育てていくんです。僕が倒れた時には「代わりに行ってくれる『ゆんぼだんぷ』いませんか?」みたいな感じにしたいです。
―――カシューナッツさんはいかがですか?
カシューナッツ:僕も以下同文ということでお願いします。
―――本当ですか?
藤原:いや、真面目な話、お互いに口にはしないものの、元々頭にあったと思うんですよ。
カシューナッツ:さっきお話した外国人にも向けて行っているお笑いライブで、白Aさんっていうプロジェクションマッピングのパフォーマンスチームとご一緒させてもらっているんですけど、そこがまさにそうで、今はもう会社化していて2〜30人のパフォーマーが在籍しているんです。1回のショーは4人とか5人でやるんですけど、ダンサー自体は10人、15人いて、同時に仕事を受けられるんです。複数のチームがいて、複数の現場で動けるようにしてみたいなんです。たとえば、今夜もここ(松竹芸能角座)でイベントをやるんですけど、同時並行でサウジアラビアで仕事もしていて、さらに企業のイベントにも出ている。同じ日に3現場とかあったりするらしいんです。その代表の方と毎週一緒に話すんですけど、「ゆんぼだんぷも、何人かいて色々なところでやったら面白いんじゃない?」と言われたことがあって。
藤原:ネタ自体も、コンビでじゃなくて、もっと大量のデブでパフォーマンスしたりもアリじゃないか、って。
カシューナッツ:白Aさんたちはお笑いの賞レースに出る方たちではないので、ステージを「エンターテイメント」として捉えているんです。だから、僕たちお笑い芸人とは広がり方のアイディアを持っているんです。その考えに刺激を受けて、僕たちも「ゆんぼだんぷ」を増やしていくのもありじゃないかって思い始めているんです。白Aさんたちのパフォーマンスはダンスなので、みなさん40歳を越えると、体力的にどうしてもキツくなってくる。初期のメンバーは今は運営側に回っていて、マネージャー的な立ち位置になったり、後輩の指導をしているみたいなんです。その話って僕たちにも言えて、体型もそうだし、いつまでも永遠にできるネタじゃないか、みたいな思いもどこかであって……。だから、「固いお笑いネタ」というよりかは、もっとエンターテインメントな方向に舵を切っていて、チームで行うパフォーマンスになっていくのも面白いかなあと思うんですよ。
藤原:芸の幅も広がると思うんですよね。M-1とかが目標じゃないから、「このふたりで舞台が完結するものをしなければならない」っていう縛りがないんです。漫才師の頂点に立つことが目標だと、どうしても規定のルールの中で考えちゃうと思うんですけど、僕らは別にないので。「マッスルミュージカル」みたいな感じでデブだけを集めたサーカスをやってもいいですね。ジャグリングができるデブとか、バク転ができるデブとか、そんなんだったら即採用です。
―――かなり面白い発想だと思います。お笑い芸人というよりも、むしろ経営者のような考え方ですね。
カシューナッツ:たまたま周りにそういう方が多くて、色々な話を聞けるので、そのお陰です。「漫才」は日本のお笑い文化のひとつとして根強いので、やり続けている人は、これからも多少は仕事が繋がっていくと思うんです。でも、そうじゃないお笑い、たとえば「コント」はどうなんだろう? とか。『キング・オブ・コント』がなくなったら、相方が突然芸人を辞めてしまったら、その時はどうするんだろう? って、ふと思う時があるんです。お笑いって、どうしてもそこがリスキーなんです。スポーツ選手だと、スポーツをやっていた経験が活かせる職場があるかも知れない。でも、お笑いは違う。
―――いわゆる「つぶし」が利かない?
カシューナッツ:お笑い芸人を辞めていった方の話を聞くと、たとえば、10年間バイトをしながら芸人をやっていて、30歳で芸人を辞めて再就職をしようって時に、その10年間は「ただの無職かフリーター」として扱われるんです。本気でお笑い芸人として頑張っていたのに、世間にとってはその程度なんです。お笑い芸人が好きだからこそ、お笑い芸人の世界の悲しさも知っているんです。認められないし、数値化できないし、資格も免許もないじゃないですか。そういう話を聞いて、自分たちも少しは考えないとな、と焦ったりするんです。
藤原:「AIに仕事を奪われる」っていう話がありますけど、お笑い芸人に限らず、どの仕事もいずれはそうなる気がするんですよね。ずっと続けていれば報われるってことはなくて、どうすればいいかを考えないといけない。
カシューナッツ:自分たちは先輩方のおかげでここまで来られたので、本当に恵まれていると思ってます。だから、それを後輩たちに返していきたいという気持ちもあるんです。下を育成していくことで返していく。お笑い芸人として生き残っていく道を示してあげられたら、繋がっていけたら、という思いなんです。
「ゆんぼだんぷ」のおふたりが出演している『ダス・スーパータレント』の予選の動画はこちら。
ファイナリストの発表は以下のURLから確認できる。
https://www.rtl.de/cms/supertalent-2020-finale-diese-12-kandidaten-kaempfen-um-den-sieg-4454492.html